
アンテナの分配器って何?メリットやデメリットについても解説
アンテナの分配器の役割とメリットについてお探しでしょうか?この記事では、複数のテレビを同時に快適に視聴するためのアンテナ分配器の基本をわかりやすく解説します。分配器の選び方や設置のポイントについて触れているので参考にしてください。
本ページではプロモーションが含まれます
当サイトでは商品やサービス(以下、商品等)の掲載にあたり、 ページタイトルに規定された条件に合致することを前提として、当社編集部の責任において商品等を選定しおすすめアイテムとして紹介しています。同一ページ内に掲載される各商品等は、費用や内容量、使いやすさ等、異なる観点から評価しており、ページタイトル上で「ランキング」であることを明示している場合を除き、掲載の順番は各商品間のランク付けや優劣評価を表現するものではありません。 なお当サイトではユーザーのみなさまに無料コンテンツを提供する目的で、Amazonアソシエイト他、複数のアフィリエイト・プログラムに参加し、商品等の紹介を通じた手数料の支払いを受けています。掲載の順番には商品等の提供会社やECサイトにより支払われる報酬も考慮されています。...
「自宅でテレビを快適に見たいけれど、複数のテレビを同時に使うにはどうしたらいいのだろう?」このような疑問をお持ちの方にとって、アンテナの分配器が役立ちます。
この記事では、アンテナの分配器とは何か、そのメリットについて解説します。分配器の導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
アンテナの分配器とは

アンテナの分配器とは、テレビを視聴する際に使用する周辺機器の一つです。アンテナの設置工事や修理に関与したことがなければ、馴染みのない機器かもしれません。加えて、分波器や分岐器など、似たような名前の商品も多く存在します。
そこで、分配器と混同されがちな分波器や分岐器についても触れながら、分配器の詳細について解説していきます。
分配器とは
分配器は、テレビ局や人工衛星から送信される電波を受信し、複数台のテレビなどで視聴できるように、電波を均等に分配する機械です。受信した電波を2つに分配する2分配器から、8つに分配する8分配器まで、多様な種類が存在します。
そのため、用途に合わせて適切な分配器を選ぶことが重要です。
分波器とは
分波器は、受信した電波を地デジとBS/CS放送の電波に分ける機械です。アンテナの設置状況によっては、地デジとBS/CS放送の電波が同じ端子を通じて送信されます。そのような場合に分波器が役立ちます。地デジ放送に加えてBS/CS放送も視聴したい場合は、分波器の使用がおすすめです。
分岐器とは
分岐器は、受信した電波の一部を分け出す装置です。分配器が電波を等しく分けるのに対し、分岐器では任意の量に電波を調整できます。これにより、メインケーブルの信号レベルを維持しつつ、必要な量の電波のみを供給できるのが大きなメリットです。
分岐器は主に、長いケーブルが必要なマンションや大規模な建物内で使用されますが、一般の住宅ではあまり使われません。
分配器を使うことのメリット・デメリット

分配器は使い慣れない機器かもしれませんが、テレビを快適に視聴するために役立つアイテムです。アンテナ分配器を使用することのメリットとデメリットについて説明します。
分配器のメリット
分配器は、2台以上のテレビや、出力したいものがあっても1つのアンテナから電波を受信し、同時に視聴できます。通常、1つの端子からは1つの機器しか接続できず、視聴可能なテレビは1台に限られます。
しかし、家に複数の部屋がある場合や、家族間で視聴したいテレビ番組が異なる場合、2台以上のテレビを設置する必要があるでしょう。
分配器があれば、同時に2台以上のテレビを視聴できるので、快適にテレビを視聴できます。また、分配器は2から8までの異なる分配数を持っており、ご家庭の使用状況に応じて選べるのもメリットです。
また、分配器にはさまざまな種類があります。
- 1端子通電型
- 全端子通電型
- ケーブル付きの単体型など
使用用途に応じて適切なものを選びましょう。
分配器のデメリット
分配器のデメリットは、分配数が増えたり、配線が長くなったりした場合、電波が弱くなるところです。分配器は受信した電波を等しく分けるため、電波は分配するたびに弱くなります。
これによりテレビの映像が粗くなったり、ノイズが入ったりすることがあり、場合によってはテレビ自体が映らなくなるでしょう。
さらに、配線作業には専用の道具が必要となる点も、デメリットです。専門の業者に依頼する場合は問題ありませんが、自分で接続を行う場合は、専用の道具を準備し、分配器本体の購入費用も考慮する必要があります。
分配器を選ぶ時の基準

分配器は、ホームセンターなどでも購入可能な周辺機器であり、分配数や通電方式の違いにより、さまざまな使用シーンに合わせた多くの種類が存在します。そのため、どの分配器を選ぶべきか判断が難しいこともあるでしょう。ここでは、分配器の選び方について、説明していきます。
視聴方法で選ぶ
地デジだけでなくBS/CS放送も視聴したい場合は、全端子通電型の分配器がおすすめです。全端子通電型の分配器は、すべての端子に通電するタイプのもので、通電がなければBS/CS放送の視聴ができません。
したがって、複数の部屋やテレビでBS/CS放送を視聴する予定がある場合は、全端子通電型の分配器を選びましょう。
設置の手軽さで選ぶ
設置を手軽に行いたい場合は、単体型の分配器が適しています。単体型はアンテナケーブルと分配器が一体化しているモデルで、初心者でも配線作業が簡単に行えます。ただし、無線LANなど他の接続する機器がある場合、ケーブルの長さを考慮しないと足らない事態になるでしょう。そのため、設置する場所をよく考慮して選ぶことが重要です。
出力端子の数で選ぶ
分配器は、出力端子の数で選びます。自分がどれくらいの分配数を求めているかを事前に確認しておくと、分配数が足らず買いなおしをしなくて済みます。
また、分配器は連結して枝分かれさせることも可能です。しかし、分配するたびに電波が弱くなるため、分配数はできるだけ少なくしましょう。テレビの台数プラス1くらいが、目安としておすすめです。
2分配型を複数つないで使用する「カスケード接続」も可能ですが、カスケード接続では、接続するたびに電波の量が、およそ3~4dB程度減少すると言われています。そのため、分配器を多岐にわたって接続すると、電波が弱まり、テレビの視聴に悪影響が出てしまいます。
可能な限り分配器の使用は少なくしたうえで、必要であれば3分配器や4分配器を選ぶようにしましょう。
周波数帯で選ぶ
周波数帯で分配器を選ぶのも大切です。地デジやBS、CS放送、4Kや8Kなどさまざまなテレビ放送があります。それらの放送は、周波数が異なるのです。
分配器においても、対応する周波数が異なるため、どのようにテレビを視聴したいかによって選ぶ分配器が変わってきます。例えば、2K放送を視聴する場合は2071MHz対応の分配器で十分ですが、4Kや8K放送を視聴する場合は3224MHz対応の分配器が必要になります。
対応していない分配器では、テレビが視聴できないこともあるので、事前にチェックすることが重要です。
価格で選ぶ
価格で分配器を選ぶ場合、同じ性能の製品であれば、低価格なものを購入します。分配器の価格帯は、安いもので約100円から、高いものでは約17,000円までと幅広くあります。例えば、2分配器の場合、価格は約2,000円から5,000円程度です。一方で、8分配器では。約15,000円から17,000円程度となります。
ただし、同じ分岐数の製品でも安価なものは耐久性が低いため、長期間にわたって使用する予定であれば、品質が高く安定している国内メーカーの製品を選ぶのが賢明です。
コンセントからの距離で選ぶ
分配器を購入する際、事前にコンセントからの距離を把握しておきましょう。テレビ用のコンセントから、分配するテレビまでの距離が近いのであれば、プラグタイプの分配器がおすすめです。
プラグタイプは、テレビアンテナコンセントに直接接続できるので、テレビ側にケーブルをつなぐだけで済みます。しかし、プラグ型は外れやすくなっています。
一方、テレビアンテナコンセントからテレビまでの距離が長い場合は、シールド型の分配器がおすすめです。シールド型の分配器には、テレビ用コンセントとの接続部にネジ式のシールドが付いており、外れにくくなっています。
そのため、距離が長い場合は外れにくく、快適にテレビが視聴できるシールド型を選びましょう。
分配器の設置を業者に依頼した際にかかる費用

分配器の設置を専門業者に依頼する際の費用は、テレビアンテナの状況や配線の距離、壁の構造、分配器の有無などの状況で変動します。工事の種類別に相場費用を以下の表にまとめました。
| 工事の種類 | 相場費用 |
| 分配器設置のみ(テレビ端子の増設や壁の加工が不要な場合) | 5,000円~8,000円 |
| テレビ端子の増設と壁の加工が必要な場合 | 20,000円~25,000円 |
| テレビ端子の増設、壁の加工、床下の工事も必要な場合 | 30,000円以上 |
| ブースターの追加設置工事 | 15,000円 |
どのような作業が必要かは、現場を確認してもらわないとわかりません。まずは、現場調査や見積もりを依頼しましょう。複数の業者から見積もりを取ることで、最も費用が安い業者の選択が可能です。
また、分配工事後に電波が足りなくなり、追加工事が発生することもあります。その場合は、追加費用が発生するため、合わせていくらになるのか業者に確認しておきましょう。
分配器を自力で接続する方法
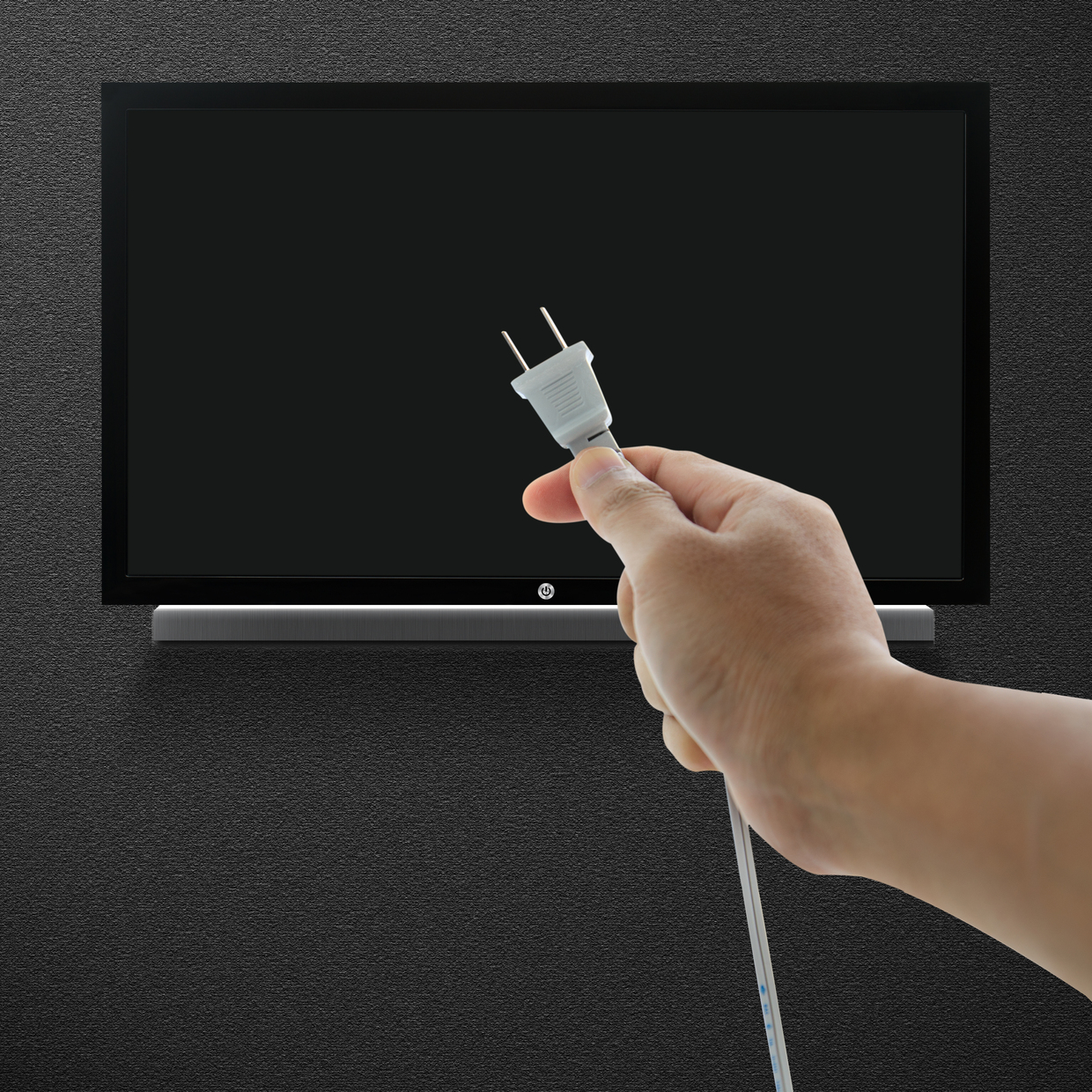
分配器の接続は、テレビの配線に詳しい方にとっては難しくないですが、初心者には複雑に感じられるでしょう。基本的には、業者に依頼して設置をおすすめします。
しかし、費用を抑えたい方は、DIYで接続することも可能です。ここでは、接続方法について解説します。
アンテナ端子が1つで地デジのみ視聴する場合
アンテナ端子が1つで、地デジのみ視聴する場合は比較的簡単に接続できます。まず、アンテナ端子から接続するテレビまでの距離を測り、必要な長さのケーブルや機器を準備しましょう。
テレビを映すための流れは、地デジアンテナからアンテナ端子、分配器を経てテレビにつなぎます。注意点は、出力と入力の端子を間違わないことです。最後に、すべてのテレビが正しく映るか確認して終了です。
アンテナ端子が1つで地デジ、BS/CS放送を視聴する場合
アンテナ端子が1つで地デジ、BS/CS放送を視聴する場合は、分配器と分波器が必要になります。接続の流れとしては、アンテナからアンテナ端子、分配器、分波器を経てテレビに繋ぐ順番です。
アンテナが地デジ専用の場合は、BS/CS放送対応にするため業者に依頼することをおすすめします。
アンテナ端子が2つの場合
アンテナ端子が2つの場合、2つのアンテナ端子を地デジのアンテナ端子、BS/CSのアンテナ端子に分かれているケースと分かれていないケースがあります。
分かれていない場合、端子が1つのパターンと同じ方法で視聴可能です。一方、分かれている場合は、分配器が2つ必要です。それぞれのアンテナ端子を分配器に接続し、テレビに繋ぐ必要があります。
アンテナ分配器を使って快適なテレビ視聴を実現させよう

テレビを2台以上使用したい時に活躍するアンテナの分配器。とても便利な機器ですが、素人には少々難しい側面もあります。
一度覚えてしまえば、分配器の接続は困難ではありません。この記事を参考に、選び方や接続方法を確認し、快適なテレビ視聴を楽しみましょう。
